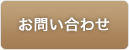初回は1時間まで5,000円(税抜き)2回目以降は30分5,000円(税抜き)
メール相談、電話相談は受け付けておりません
~熊野量規法律事務所は、地域密着型の法律事務所として、地域の皆様の良きパートナーとして多くの皆様に気軽にご相談いただける法律事務所を目指しております~
相続における特別受益|対象となる財産や時効など
相続における特別受益|対象となる財産や時効など
相続人の一部が被相続人から生前に財産などを受け取っていると、遺産分割の際に相続人間で揉めてしまう原因となりえます。
そこで、特別受益という考え方があります。
当記事では、特別受益について詳しく解説をしていきます。
特別受益とは
特別受益とは、一部の相続人が相続に先んじて被相続人から財産を受け取っていた場合に、他の相続人との間で公平を期すために、遺産分割の際に先んじて受け取っていた財産を計算に入れた上で、分割協議を行うための制度となっています。
例えば相続人が2人いて、そのうちの1人が被相続人から生前に1,000万円を受け取っていたとします。
この状態のまま遺産分割を行うと、もう1人の相続人が損をしてしまうため、分割された財産から1,000万円を差し引いて計算を行います。
このようにすでに受け取っている財産を差し引くことを、「特別受益の持ち戻し」といいます。
もっとも全ての財産が特別受益の対象となるわけではありません。
次に特別受益の対象となる人物と対象財産について解説をしていきましょう。
特別受益の対象者
特別受益の対象となるものは相続人だけではなく、特別受益の対象となる財産を取得している者のことを、特別受益者といいます。
以下では、特別受益者となり得る人はどのようなものかご説明します。
- ・推定相続人
- 推定相続人は、被相続人の死亡により、法定相続人となる可能性が高いもののことを指します。
推定相続人は当然に特別受益者に該当します。 - ・代襲相続人
- 代襲相続とは、本来相続人となるものが死亡したり、相続欠格や相続廃除となった場合に、その相続人に子がいると(被相続人から見て孫にあたる)、相続権を代襲して、行使することができます。
代襲相続人は、代襲原因が発生する前に贈与を受けた場合であれば特別受益者に該当することはありませんが、代襲原因発生後に贈与を受けた場合には、特別受益者に該当する可能性があります。 - ・婚約者、養子になる予定の者
- 婚約者や今後養子縁組により被相続人の養子となる予定のものに関しては、いずれ相続人としての地位を手に入れることとなるため、特別受益者となる可能性があります。
これらの者たちが受ける贈与の内容としては、婚姻や養子縁組に伴って渡される財産となります。 - ・相続人の配偶者や親族
- 相続人の配偶者や親族は法定相続人にも推定相続人にも該当しないため、原則として特別受益者となることはありませんが、被相続人が相続人の配偶者に対して財産を贈与したことにより、相続人が何かしらの利益を得ている場合には、相続人が特別受益者に該当する可能性があります。
- ・高額な金銭、有価証券、金銭債権
- お小遣い程度の金額であれば、特別受益となる可能性は非常に低いですが、高額な金銭や有価証券、金銭債権の贈与があった場合には、特別受益の対象財産となる可能性が高くなっています。
- ・不動産
- 不動産は高額な財産の代表例となっているため、不動産の贈与があった場合には、当然に特別受益が認められます。
また、直接不動産の贈与を受けたわけではなく、不動産の購入資金を受け取った場合にも、特別受益が認められます。 - ・婚姻や養子縁組に伴う金銭
- 婚姻や養子縁組の際に贈与された財産についても、特別受益の対象となります。
婚姻の場合であれば結納金や結婚式の費用などがこれに該当します。
もっとも少額の場合であれば扶養の範囲内として処理されるため、特別受益には当たりません。
養子縁組は養親だけではなく実親の相続人にもなります。
そこで養子縁組が始まる前に実親が財産を先渡ししていたような場合には、この財産が特別受益の対象となります。 - ・借地権
- 被相続人が所有している土地の上に、相続人が建物を所有していた場合には、借地権が実質的に贈与されているとみなされ、それに相当する額が特別受益の対象となります。
また、借地権が被相続人から相続人の名義となっている場合であっても同様です。 - ・高等教育の学資 大学の学費や留学の費用などは高等教育の学資として、特別受益の対象となる可能性があります。
特別受益の対象となる財産
特別受益に該当するかどうかは、被相続人の生活水準や教育水準などから判断することとなります。
例えば贈与した財産が同じ1,000万円であっても、被相続人の年収が2,000万円であれば特別受益と判断される可能性が高くなり、年収が1億円の場合には特別受益に該当すると判断される可能性が低くなります。
教育水準については、後述します。
しかしながら、昨今では大学の進学率もかなり上がってきており、一概に特別の利益に該当するとは言えません。
そこで判断基準としては、学資を贈与したものが受けてきた教育水準などを参考に判断することとなります。
贈与者の家系において、高等教育を子どもに受けさせることが一般的である場合には、特別受益に該当することはありません。
特別受益に時効はある?
結論から言うと、特別受益に時効という概念はありません。
しかしながら、特別受益の対象となる財産は、相続開始前の10年以内とされているため、不当に昔の財産を特別受益とみなされることはありません。
特別受益の問題は、法律の専門家抜きで解決することは非常に難しい状況であることが多くなっています。
そのため、現在特別受益でお困りの方は弁護士に相談することをおすすめします。
熊野量規法律事務所では広島市を中心に、相続問題を取り扱っております。
特別受益に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご相談にお越しください。
熊野量規法律事務所が提供する事例・相談内容
-
実況見分調書

- 実況見分調書とは、人身事故を起こした際に 警察が現場検証を行って、事故の様子を細かく...
-
残業代

- 未払い残業代の請求は、あなたの正当な権利です。労働問題を数多く取扱う弁護士が相談時か...
-
労働基準監督署

- 労働基準監督署とは、労働基準法その他の労働者保護法規に基づいて事業場に対する監督及び...
-
相続税対策

- 相続税改正により、2015年1月1日から、基礎控除額が引き下げられ、最高税率が引き上...
-
相続放棄

- 相続開始後に、相続人が相続を拒否する意思表示。3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要が...
-
法定相続人の範囲と順位

- 被相続人が遺言をしていなかった場合、民法に定められた相続人が、民法に定められた割合で...
-
企業法務

- 当事務所は、地域の人々が身近に感じていただける法律事務所を目指しています。 企業経営...
-
寄与分

- 共同相続人間の公平をはかるために共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の働...
-
交通事故の時効

- 保険会社との示談交渉は、慌ててサインするべきではなく弁護士に相談し納得できる示談内容...